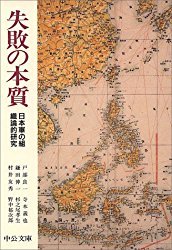高木 徹 / ドキュメント 戦争広告代理店〜情報操作とボスニア紛争
 知人が「面白かった」とおすすめしてくれた本。
知人が「面白かった」とおすすめしてくれた本。リアルサスペンスですね。面白かった。
いろいろな意味で視野が広くなる良書です。
4人が織りなすノンフィクション「PR」サスペンス
ジャーナリストを名乗る方の記事や文章というのは、いかに正しく情報を拡散するか、という視点から、予備知識があることを前提とした、少々難解なカタい文章であることが多いと思う。そうなってしまうのは仕方がない。
そんななか、この本は「中東(ボスニア・ヘルツェゴビナ)の紛争のPR」という複雑な題材を、少数のキーパーソンが何を考え、どのように動いたのかという視点からドキュメンタリーとして描く。
「紛争✕PR」 ?
ぱっと見異質に見える要素だが、PRとは「その人にそうなってもらうための戦略」全般と思うと分かりやすい。
Public Relations なので対象は「公共」つまり不特定多数と考えられますが、ここでは「世論を作る」ことで政治家を動かすという手段と考えてよさそうです。
ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争は、1992年~1995年まで続いた戦争で、概ね「ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国(モスレム人)」VS「セルビア共和国(セルビア人)」という構図での争い。
キーパーソンは4名。
- 「PR戦争」を仕掛けるブレーンである「ジム・ハーフ」
- ボスニア・ヘルツェゴビナの外相として世論づくりの顔となる「シライジッチ」
- セルビア共和国の大統領で「悪役」を務めることになってしまう「ミシェロビッチ」
- セルビアの悪評を奪回しようとしたアメリカ国籍のユーゴスラビア連邦共和国首相「ミラン・パニッチ」
そこで、小国とはいえボスニア・ヘルツェゴビナの外相(シライジッチ)が、アメリカに軍事介入してもらうためのPRを、アメリカの民間PR企業(ジム・ハーフ)に依頼するところから始まります。
4名について、本人の言葉はもちろん、筆者自身の印象や、関係者の言葉を紹介しながら、人物像が浮かび上がってくるような鮮やかな描写。
そしてあくまでジャーナリスティックであろうとする書きっぷりと、それでも漏れ出てしまう著者のジレンマ。
「アメリカの軍を動かすPR」というスケールの大きい非日常テーマはまるで土曜夜のサスペンスドラマです。
結末を先に言ってしまえば、アメリカが軍事介入するという結末にはならないのですが、ボスニア側に喜ばしい世論が形成されていき、ミラン・パニッチ首相(ユーゴスラビア連邦共和国)が国際会議の場で国連を追放されてしまいます。
ご都合主義的なフィクションじゃあるまいし、それらは全てハーフらのPRによるものだ、と言い切ることは出来ませんが、少なからず世論を形成し、他国の要人を動かす要因となったのもまた、間違いではないでしょう。
PRに関する理解
もし、「日本の対世界的交渉のコンサルテーションとアレンジをアメリカ民間企業に依頼する」と耳にすれば、「え!? そんなことしていいの!?」「ていうかそんなことしてくれるの!?!?」と、反射的に思ってしまう日本人(私)。「そんなこと」というのは、国家に関わる機密情報(というか自国の運命を大きく揺るがす外交政策)のコントロールを民間人…しかも他国の…が行ってよいのか、という感じですね。
ま、倫理的な議論はもちろんあるかと思いますが、少なくともアメリカを中心として世界はそういうことを行っている。
本書では、セルビア側だけが一方的に非人道的な殺戮や侵略を行っていたわけではないが、ジム・ハーフの戦略とシライジッチの名演説によって徐々に「セルビア=悪」「ボスニア・ヘルツェゴビナ=被害者」という世論ができてゆく流れを丁寧に追っていきます。
ワシントンは「メディア」「政権」「連邦議会」の三角形で成り立っていて、「軍事介入を決断させる」とはつまり「政権」を動かすということなのですが、そのためには他の2つ「メディア」「連邦議会」を動かせばいい…。
政権も連邦議会も、政治家が政治生命を掛けて戦う場でもあるわけですから、メディアや世論の論調が傾けば、それが少々真実と違っていたとしても、逆張りするのは非常にリスクが高いわけです。
まして、これをPRのプロが本気で仕掛けてきているのであれば、それに対抗しうるPR戦略をもって立ち向かわねばならない。
安易に自説を繰り返して「真実を述べたまでだ」と満足しているだけでは、事態を覆すどころか自分自身の進退をも危険に晒すことになるかもしれない…。
本書では国連軍の「マッケンジー将軍」が、まさにそうなってしまった方…といった感じで紹介されています。
もともと紛争の舞台となるユーゴ地域の人々は、「真実はいつか明らかにされ、悪も正義も正しく処置される」みたいな考えを持っているらしい。
どっかで聞いたような?(※日本)
だけど、「劇的」がお好みのアメリカのプロが本気で、こちらに都合の悪いPRを展開してきたら、いったい誰が「明らかに」して「正しい処置」を取ってくれるというのか。
勝つための戦略
「脳ある鷹は爪を隠す」…じゃあないけど、どうも自分を含めて、日本人は「扇動」にある意味類する「広告」「宣伝」「アピール」とかをあまり心地よいものと思っていないフシがある気がする。なんというか「良いものは、なにもしなくても、見てくれている人がいて、いつかちゃんと評価されるのだ」みたいな。
「盛る」のをあまり美しいこととしないというか。
謙遜が評価されるくらいだから、「自分はこんな点をアピールします!」と言ったとすると「(無駄に)尊大な態度で失礼である」とか「弱い犬ほどよく吠える」とか…。
これはなんだろうね、歴史的もしくは民族的ななにかなのかな。儒教かなにか?
じつは「お互いのために戦略的にPRする」というテーマに興味を持っていた時期があった。
その時は「不特定大多数に向けて大金つぎ込んでブッパするTVCMのようなものではなく、株主と信頼コミュニケーションをやり取りするIR」に興味があったのだけど、これってやっぱりどこか「不必要に盛るのってよくない」「外側だけ取り繕って良く見せるって事自体がなんだか信用ならない」みたいな考えがあったのもあるんですよね。
ある程度特定の人物に向けて「真摯にやれば、きっと分かってくれるはずだ」みたいな。
「一方的な広告ではなくて、心と心のコミュニケーション」みたいな。笑
まあ、ぶっちゃけビジネスでも人間関係でも行き着くところは「真摯・信念・信頼」だと思っているので(たぶん松下幸之助とかも似たようなこと言ってると思う)、それを捨ててまで誇大表現したり、挙げ句に偽装工作(嘘をついて)宣伝しろとは思わないけど、勝つための戦略を練らずに「いつか誰かが評価してくれる」みたいな修行僧みたいなことばっかり言ってたら、「負ける」よ、と。
いかに世界(世間)を正しく把握し、そしてその中に位置する自分(達)の立ち位置を正しく理解し、それぞれの特徴を掴んだ上で、誰にどうなってもらうために何をするか、という、わりとロジカルな取り組みであると思う。
普段の仕事でも、そして政治や世界を見るという意味でも、非常に良い学びとなりました。
政治に対する一有権者(善良な一市民)としては、できる限り「真実」を見極められるよう、安易に気持ち良い言葉やドラスティックな表現に流されてしまわないよう、慎重になりつつも、
普段の仕事や私生活では、「戦略的にPRする」という武器を駆使していけたらと思います。