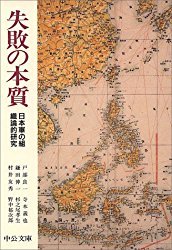ナディーン・ラバキー / 存在のない子どもたち(Capharnaüm)
 @シネスイッチ銀座にて。
@シネスイッチ銀座にて。とにかく、主人公であるゼイン少年がイケメンすぎる。
もはや理由はこれだけでいいです。堅くて暗い内容だと思って敬遠せず、ぜひ観ましょう!
がっつりネタバレしていますので、読みたくない方は公式サイトのキャスト欄をぜひどうぞ。
中東のいまを丁寧に切り取る
もう一度、公式の本サイトはこちら。http://sonzai-movie.jp
あらすじは、中東で貧困な暮らしを強いられている、およそ12歳ほどの少年が、「僕を産んだ罪」で両親を訴える、という内容。
・・・という触れ込みになっています。
私はてっきり裁判で互いが問答したり判決を下すといったシーンを描くのかと思っていたのですが、そういうシーンはあまりありません。
12歳の少年が自分の存在を公に否定さえしたくなる、壮絶な人生を歩まねばならなかったのはなぜか。そういう視点で、ゼインの苦悩を丁寧に描いていきます。
政治情勢的な描写はほぼ皆無で、あるのはただただ、生き延びるのに必死にならざるを得ない、心の優しい少年ゼインの悲壮な日常。
そもそも戸籍を持っていない両親のもとに生まれ、妹や弟たちと道端でジュースを売ったり、薬物を売ったりして家族でなんとか食いつないでいる。
そして大切な妹を売られてしまったショックから、ゼインは家出をします。
(まあ、ショックというより「両親に対する絶対的な軽蔑」ですかね…)
とある女性の赤ちゃんを世話する代わりに居候を許されるという形になりますが、その女性も不法滞在者として逮捕されてしまう。
きっと誰も悪くないのに、みんなが不幸になっていく。。
12歳の男の子がですよ。
自分さえ明日生き延びるためにどうしたらいいか分からない、という状況なのに、赤の他人の赤ちゃんを、どうしても見捨てられずに頑張って食べさせようとするわけです。フィクションとわかりつつも、優しすぎて切なすぎました…。
それは「居候を許してくれた女性への義理」なのかもしれませんが、それよりもシンプルに「命を大切にしなくてはいけない」という使命みたいなものだと思うのですよね。
結局、ゼインは悩んだ末に赤ちゃんを人売り(例の偽戸籍と国外逃亡斡旋するヤツで、表向き養父母が見つかったとゼインを説得し続けた)に預け、自身は亡くなってしまったことが分かった妹の仇を取るため買い取った人物を刺してしまい、牢に入れられます。
裁判というのはこの後に発生し、映画自体は裁判所の中でゼインと両親らが相対し、状況を回顧するというふうに始まっています。
この時点で「必死に守ろうとした妹が売られて亡くなってしまった」という大きな絶望、つまりゼインが両親を訴えるに至ったきっかけの一つはほぼ描ききっている状態です。
隣の席の女の子も号泣してました。
でも実は私が一番グッときたのはこの後、クライマックスのなかでもかなりフィクションくさい1シーン。
12歳の無戸籍かつ牢に入ってる犯罪少年が、どうして「産んだ罪で訴える」などということを実現できたのか。
「リアルタイムで視聴者からの法律電話相談を行う有名なテレビ番組」に、ゼインの電話がつながるのです。
12歳の囚人の電話が有名なテレビ番組に繋がって生放送で放映される、というだけでも衝撃ですよね。
そして、「両親を訴えたい」と語るゼインの言葉に、そのテレビを観ていた少年囚人者たちが一斉に湧くんです。
このシーン、ゼインと同じように本来は心優しく真面目(だったかもしれない)な少年たち、もしくは不条理な理由で捕らえられている人たちがたくさんいる、ということを示唆していたと思います。
だからグッときた。
もちろん、世間でも大いに話題になったんでしょうね。
それで法廷の場を設けることができた。
本作で焦点が当たったのはフィクションの「ゼイン」だけど、「似たように不条理にさらされて戦っている人たちが大勢いる」というのは大事なメッセージでしょう。
不条理さをなんとかすること、
自分自身が強くあること、
を改めて突き付けてくる良作と思います。
フィクションのぎりぎりに挑む
この作品の大きな特徴の一つとして、「作品内のキャラクターと似たような境遇の素人」を、本作のために現地にて起用しているということ。監督はどうやら前作もこの手法で撮っていて、その作品も評価が高いようです。
確か「IN THIS WORLD」という映画でも同様の手法を取っていて、本作と同じく「キャストの人たちはその映画をきっかけによりよい現在を送っている」という後日談付き。
これ、本気でやると、ジャーナリズムやドキュメンタリーよりもリアリティがあるんだなと感じました。
ジャーナリズムは「いかに現在を、今生きている人に正しく伝達するか」が重要と思うし、
ドキュメンタリーは「実録として事実を記録する」が重要と思うから、
そこには「製作側の思想」をできるだけ入れ込まないことが大事な点だと思います。
でも社会派フィクションって「わざわざ創作にして伝えたいことがある」という監督の想いがある。
どうやって琴線に訴えかけようか。
ただただ第三者視点から「大変ですね」とカメラを回すのではなく、自分事だと思って共感してほしい、そういう意図で制作陣が本気でぶつかってきているパッションを感じる。
これって「中身はフィクション」だけど、そこに描かれていることはまさに「本質」や「リアル」で、フィクションを介しているからこそ「リアル」をより体感できる、そんな感じなんじゃないでしょうか。
伊丹十三氏が、脅されてもマルサの映画を放映し続けた、というのを思い出しました。
こういうパッションフィクション映画(新ジャンル爆誕!)は本当に見ていて勇気が湧いてくるね。
フィクションで他人を都合よく洗脳・扇動するタイプのものもある(極端に言えばオウ〇とか)からセンシティブな問題なのでしょうけれど、間違え続けないように見極めつつ、素晴らしいパッションフィクション映画は応援していけたらなぁと思います。
[amazon_link asins=’B0001WGLZ0,B00FYM1GE8,B002BBEOQW’ template=’ProductCarousel’ store=’universe000-22′ marketplace=’JP’ link_id=’c1b25f95-a6b9-41e0-8f1f-4b255713fc05′]