山本 有三 / 路傍の石 (新潮文庫)
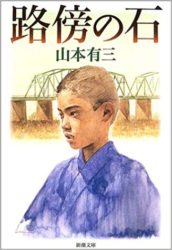 昭和史を復習中。時代を感じる名著です。
昭和史を復習中。時代を感じる名著です。面白くて一晩でイッキ読みしてしまいました。
新潮文庫・昭和55年発刊版。
道端の石ころが大成するまで
1900~30年頃の日本が舞台の立志小説。主人公の「吾一」は勉強のできる、負けず嫌いで優秀な男の子。
けれど父親のせいで、中学校(ちょうど今で言う中学校。当時は後に高等小学校)に上がらせてもらえず呉服屋に丁稚奉公に出されてしまう。12歳にして身が張り裂けそうな辛さを味わいながらも、自らいろいろな経験を経て成功してゆく。
力強く、誰かのせいにせず、自らの志と勤勉によって大成すべし、という強いメッセージ。
色々な人物が登場しますが、キーパーソンはこの5人。
- 優しく根気強い母
- 時代は変わったのに士族の矜持を捨てられない頑固な父親
- 本を読ませてくれた書店(稲葉屋)の店主安吉
- 深い縁となる教師の次野
- 転機を与えてくれた画家の黒田
吾一は序盤から一貫して非常に強い自我を持っている少年として描かれるので、「誰々が導いてくれた」のようなご都合な展開はあまりありません。と同時に、「誰々のせいで」と人のせいにして自らの歩みを止めるということも無い。
様々な出会いから自ら学び、そして実直に働きながら糧にしていくという、かなり泥臭い展開がずっと続きます。
後半、やっとそれが実になりはじめ、そしてそうなり始めてからも慢心せずにトライし続ける姿勢から、「あぁ、辛い少年期を経て、やっと花開き始める」と読者も徐々に溜飲が下がり出します。
大人なったからと言って都合のいいことは起こらず、困難は引き続きたくさん出てきます。
でも、おそらくもうこの吾一なら困難に立ち向かいながら志を成していくに違いない…。
というところで「ペンを折る」が入り、時代の流れ(第二次世界大戦前なのでリベラルっぽい描写がアウト)で連載が終了してしまうという超展開。「完結していない」ということをよく知らずに読んでいたので、「ペンを折る」を読んでいて最初は冗談かと思ったほどです。
それも含めて、ただの「立志小説」なだけではなく、時代を考えさせられる作品ですね。
ちなみに、読書中に連想した他作品は「こころ」と「十二国旗」。
「こころ」は時代がもろ被りしているから。乃木大将の殉職が1912年だから、まさしくだね。
「十二国旗」は主人公が困難に立ち向かい実直に成果を出していくというところ。
(※ちなみに「十二国旗」もそうだけど、困難があるたびにいちいち「なんぞ」と自分を奮いたたせる、みたいな少年漫画的なわかりやすい展開ではなく、むしろ「困難ゆえに諦める」ということをしない、ただただ耐えて諦めない、という感じですね。)
作者(山本有三)の自伝小説?
昭和12年(1937年)に朝日新聞で連載されていたのが最初らしい。作者である山本有三氏自身、15歳のときに呉服屋に丁稚奉公に出されて1年で逃げ出しているということなどからも、自伝的小説と言われる事が多いらしいのだけれど、本書のあとがきでもそれは否定されています。
あとがきで相違点を述べてくれてありますし、文末にちゃんと山本有三氏の年表が載っていて、ざっと見ましたが、確かに違います。
まぁでも、頭脳明晰な少年が若くして丁稚奉公させられたあと、そこから逃げ出して、自ら「立志」してもがきながら文章の道で大成していく、という大筋で言えばご本人と同じですね。
時代背景
作品中、「今から50年前の出来事」として「ノルマントン号事件(1886年)」と記されていれていますが、それは書き手側のメタ記述(連載が1937年)だと思われるので、1900年頃が物語の序盤と思われます。(そういえばちょくちょくこの「メタ記述」が出てきます。私は混乱するのでちょっと苦手です。)
吾一の登場時は「高等2年(当時の尋常小学校6年とされている)」ということは12歳。
吾一が中学校に進学できずに丁稚奉公に行って数ヶ月、はじめてのお暇で実家に帰ったときに「条約改正(明治27年/1894年)」、19歳のときに「日露開戦(明治37年/1904年)」の号外が配られた、という記述があります。
1894:条約改正(12歳?) ※ちなみにこの年、日清戦争
1904:日露開戦(19歳?)
と考えると計算が2~3年ずれるのですが、まあだいたいこのあたり、ということでしょう。
ちなみに山本有三氏は、1887年(明治20年)生まれ。
15歳で一度丁稚奉公に出されるが、1年で逃げ出しその後、東大を経て人気作家となってゆく。
50歳のとき(1937年/昭和12年)に朝日新聞にて本作「路傍の石」の連載を開始。
60歳のとき参議院議員となる。
「路傍の石」の他に、もう少し若い頃に書かれた「女の一生」や「真実一路」も有名ですね。
とにかくこの明治維新(1868)~日清戦争(1894)~日露戦争(1904)あたりの時代は激動も激動です。
- 列強に食われないよう政治と軍事
- 不平等条約の改正へ(1858年の安政五カ国条約)米・露・阿・英・仏
- 中国(清)、とくにロシアに食われないよう西側進出
- 士族の没落と商売の隆盛
「ソローキンのみた桜」でも見たように、対外戦争が日清・日露で初めてだったので国際法を遵守しようと頑張っていたようだ。
乃木大将、そしてドイツ
さていきなり乃木大将。本作にはその名前は確か一切出てきていません。ただ、この時代を代表する有名人なので。
「こころ」で先生が「明治天皇が亡くなり乃木大将も殉職した」といって自死するというシーンがあり、かなり印象深い出来事です。これが大正元年であり1912年。
この乃木大将、西南戦争で活躍した後、日進戦争、日露戦争でも活躍し、そのあと殉職となるわけですが、日清戦争に赴く前にドイツ留学をしているのですね。このドイツ留学を期に、いわゆる厳格な軍人精神を強く体現する人物に変容したらしい。それが、第二次世界大戦まで通じる日本軍の強固な精神論に結実していく。
あれ、ドイツ・・・・・。
そう、山本有三氏、ドイツ文学専攻なのですよ。
して、吾一が終盤で成そうとしていたのは、ドイツ文学にもあるような「立志小説」。
ガッテン。
この頃のドイツと日本の関係、また、ドイツの状況というのを全然分かってないけれど、かなり影響が強かったようですね。当時は最先端の国だったのでしょうか。あるいは割と負けず嫌いで潔癖主義というか、日本人とはサムライスピリッツ的な類似点があるようにも感じました。
さて、最後に小言。
サムライスピリッツ的な意味では、吾一の父親は頑ななところとか、その素質はあったはず…だと思うのです。
「生きる」ことより「面子」が大事だと喚き散らして一家を離散させ(ていうか捨てた)、挙げ句、やっぱり生きていけないとなったら、成功しはじめた息子に取り入ろうとしてくる、本当に情けない。
中盤、父親はギリギリ士族だった祖父に「士族学」のようなものを叩き込まれてしまったがために、こんな思想となってしまった、といった経緯描写があり、また、彼は彼なりに妻を愛していたのでは?とも取れるシーンも一部あるのですが、本当にそうだったとしたら、そんなのただのオ◯ニーです。
実在すると思うんだよねぇ、こういう人…。
フィクションなんだからそんなに嫌悪感を感じる必要もないはずなのですが、妙にリアルなので、なんだかモヤっとしてしまうわけです。
「他人とともに生きる」という意味が本当に分からない人というのが、本人にはなんの悪気はなかったとしても、ちょっと辛いなぁ、と思うのでした。
















